|
● |
薬理学教室 |
病気やケガによる炎症を
細胞レベルまで研究 |
炎症反応の際には「腫れ」「熱」「痛み」「白血球を呼び、活性化する」など、多様な反応を起こす生理活性物質が産出されています。これらの物質がどんな役割を果たしているのか、生体としての反応から遺伝子の発現まで、幅広い視点で研究を行っています。
[主な研究テーマ]
| ・ |
炎症モデル動物、炎症性細胞 (好中球、マクロファージ)を用いたプロスタグランディン(PGE2)合成関連酵素の遺伝子解析と蛋白発現機序の解析 |
| ・ |
炎症・発痛反応におけるメディエーターの解析 |
| ・ |
虚血・再還流誘発脳梗塞における炎症性細胞の情報伝達異常(亢進)と神経細胞脱離の機序の解析 |
|
|
 |
|
● |
分子薬理学教室 Home Page |
薬が効く仕組みを生命の
メカニズムから解明し、創薬へ |
生体内で薬が効く仕組みを、「生命のメカニズム」という根本の部分までさかのぼって研究するのが分子薬理学教室。研究対象は遺伝子、タンパク質・糖・脂質、細胞、組織、器官、全身と幅広く、こうした仕組みの解明が、新たな薬へのヒントにつながっていきます。
[主な研究テーマ]
| ・ |
GeneからWhole Animalまで、生命現象を様々な角度から解析する分子薬理学的研究を通じて、創薬に結びつく新たな薬物作用機序の発見を目指す |
|
|
 |
|
● |
薬剤学教室 Home Page |
投与された薬の「その後」を
追跡し、制御する方法を研究 |
薬剤学教室では体内に入った薬物を輸送する担体と薬物代謝に関する研究を行っています。その仕組みを知ることで、目的地(作用部位)に正しく到達するよう、また到達する割合が高まるよう、飲んだ後も薬をコントロールできる方法を確立するのが目的です。
[主な研究テーマ]
| ・ |
消化管における輸送担体を介した薬物の吸収機構の解明と吸収性の予測に関する研究 |
| ・ |
ヒト肝組織などを用いたin vitro試験に基づくin vivo薬物代謝及び薬物間相互作用の定量的予測 |
| ・ |
肝における、薬物トランスポーターを介した薬物/異物の取り込み機構に関する定量的解析 |
| ・ |
立体選択的血漿蛋白結合に関する研究 |
|
|
 |
|
● |
薬品分析学教室 Home Page |
今まで知られていなかった物質の
新しい働きを解明し、新薬開発へ |
我々の体内には、これまで知られていなかった物質が数多く存在します。これらの物質を検出し、その働きを様々な研究手段を使って明らかにする研究をしています。新しい発見は、新薬の開発へ繋がるはずです。
[主な研究テーマ]
| ・ |
これまでの常識では存在しないといわれていたD型アミノ酸の機能解析 |
| ・ |
タンパク質中の異性化アミノ酸残基の機能解析 |
|
|
 |
|
● |
和漢薬物学教室 |
免疫異常やインフルエンザに
漢方薬が効く仕組みを解明 |
膨大な経験則から生まれた漢方薬は、「どの成分が、どんなふうに効くのか」は未解明な部分が多く残っています。和漢薬物教室では北里研究所東洋医学研究所との協力で、免疫異常、インフルエンザウイルス感染などに漢方薬が効く仕組みを臨床例をもとに探ります。
|
|
 |
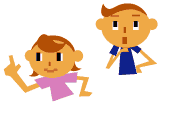
|